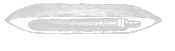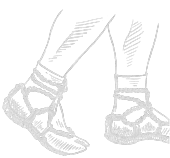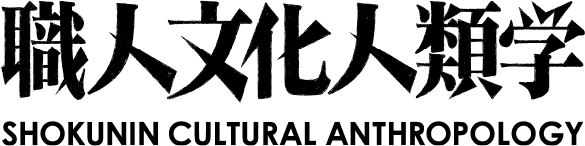【大黒屋】二十一代目・橋本彰一との出会い
あまり長い文章を書くと、読む方も書く方も大変なので、
なるべく端的な文を・・・と書いているこの文が無駄ですね。
スタートばかりした、デコ屋敷本家大黒屋での弟子入りストーリー。
そもそも、そんな職人との出会いは?!
私ら仕立屋と職人は、伝統工芸とは縁もゆかりもなく生きてきた。
キッカケは、メンバーの石井がロンドンから本帰国してすぐに、
ふらふらしながらアーティスト・イン・レジデンスに参加したこと。
舞台は郡山市。居候先がこのデコ屋敷大黒屋だった。
「一ヶ月近く居候させてもらって、何もしないわけにゃいかねぇ。」
美大出身で絵も得意な方だったので、手伝いを買って出た。
すると、お母さんたちが少しずつ、”お家”の話をしてくれるようになった。
みんなにとっては、急に現れた絵を描く異星人だろうと思っていたが、
受け入れてくれるのは早かった。
彰一さんは、その異星人の話が聞きたいと、
郡山の定食屋へ連れて行ってくれたり、
古民家で呑んでは、お互いに”モノヅクリ論”を繰り広げた。
「元美術教師で、15年以上前に先代が体調を崩し戻って来た。
教えるのが好きだ。ダメな子ほど応援したくなる。」
お店には毎日と言っていいほど、町の人が彰一さんに会いにくる。
なるほど、兄貴気質なワケだ。
「伝統を守るにはさ、守ってばかりじゃダメなんだよね。
変わり続けなきゃなんないんだよ。」
彰一さんは、若くして二十一代を継ぎ、紙でメガネをつくったり、
2mのダルマをつくったり、居候を受け入れたり、とにかく泳ぎ続ける。
この時から、私らは彰一さんを
攻める張子職人
そうみんなに紹介するようになった。
ある日彰一さんが言った。
「何か、自分が張子職人だ、という証がほしい。」
ぼくらは、攻める張子職人の魅せる作業着を仕立てることを決めた。
服は見られる意識を高める。
袖を通せば本人の気分があがる。
そのためにも、彰一さんの哲学を知らなければ。
機能性をもたせるために、しごとを知らなければ。
工房の雰囲気やお母さんたちのことを知らなければ。
そうして、弟子入りを願い出て、作業着づくりがはじまった。
フーテンデザイナー 石井挙之